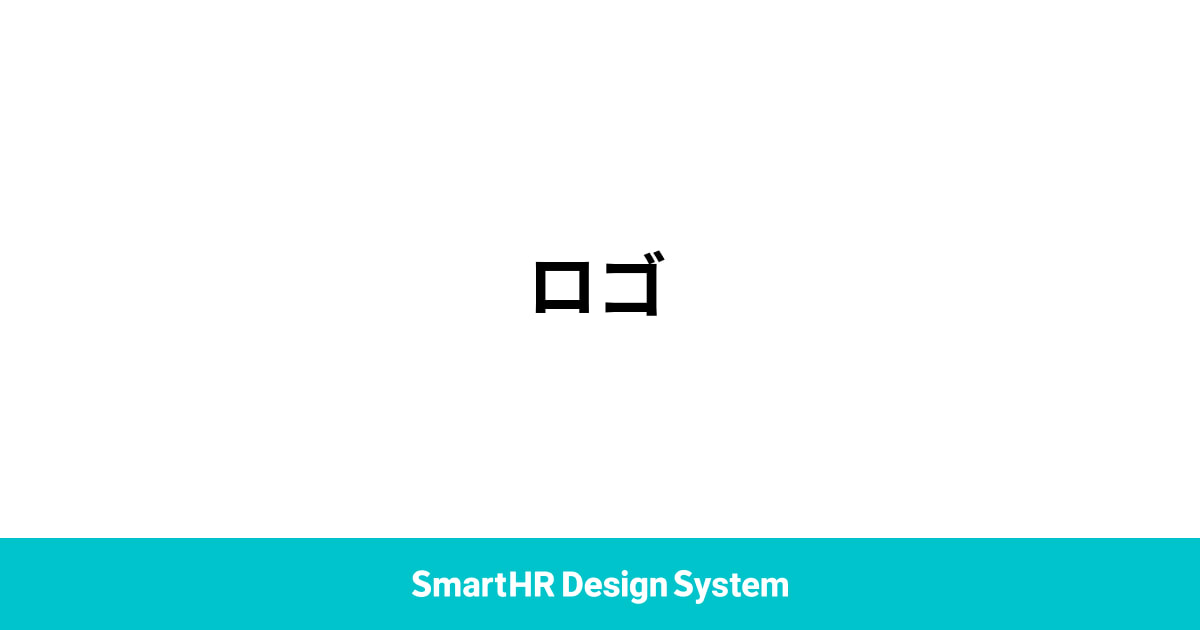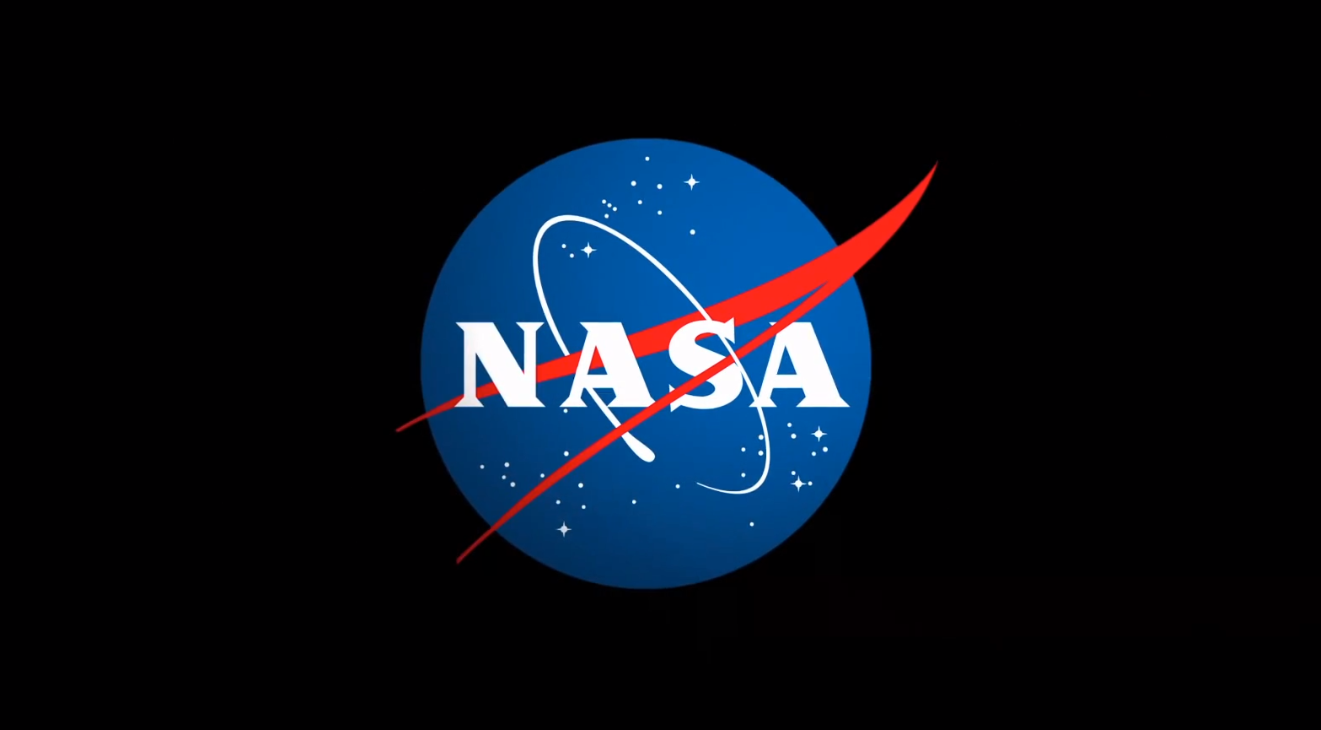皆さんは「ロゴガイドライン」という言葉を聞いたことがありますか?完全に理解している方もいれば、なんとなくイメージはできるけれど具体的な内容までは知らない、という方もいらっしゃるでしょう。
本記事では、ロゴガイドラインの目的や構成要素を分かりやすく解説し、実際の事例も交えながら、その重要性について詳しく説明します。
ロゴについて詳しく知りたい方はこちら!
目次
ロゴガイドラインとは
実は、ロゴガイドラインとは簡単に言えば、ロゴの「取扱説明書」のようなものです。ロゴの正しい使用方法やルールを明確にするために作成されるものであり、ロゴレギュレーションとほぼ同じ意味で使われる場合が一般的です。
ロゴガイドラインの目的・なぜ必要なのか?
ロゴガイドラインを設定する一番の目的は企業やブランドの一貫性を保ち、ブランドイメージを損なわないようにするためです。ロゴガイドラインには、ブランドアイデンティティを維持するために必要なロゴの使用方法やデザイン要素などがまとめられてあります。より具体的に言うと、サイズやカラーなどに関する規定が細かく記述してあります。
これにより、社内外のあらゆる関係者がロゴを正しく使用でき、ブランド価値が一貫して維持されるのです。したがって、ロゴガイドラインは企業の信頼性を高めるうえで非常に重要な役割を果たします。
さらに、多くの企業では、プレスキットという形でロゴや関連素材をまとめたデータを提供しています。このプレスキットを作成する際にも、ロゴガイドラインが基準として活用され、メディアやパートナーがブランドイメージを正しく反映する助けとなっています。
プレスキットについて具体的にご覧になりたい方は以下のセブンデックスのプレスキットをご覧ください!
ロゴガイドラインを設定するメリット・効果
ブランド情報を正しく伝えられる
ロゴガイドラインがあると、誰が制作しても同じ印象でブランドを伝えられます。色やサイズ、余白などのルールを決めておくことで、「なんとなく」の判断によるバラつきを防げます。名刺やWebサイト、SNSなど全ての接点でロゴが統一されることで、ブランドの世界観や信頼感がブレずに届き、企業イメージが定着しやすくなります。結果として、認知度や好感度の向上にもつながります。
ブランドの信用性・権威性の担保
ロゴガイドラインは、ブランドの信用性や権威性を支える「きちんとした運用ルール」です。色や形、使用NG例まで明確にしておくことで、どの媒体でもロゴが整った状態で使われ、「管理された信頼できるブランド」という印象を与えられます。逆に、人や媒体ごとにロゴの見え方がバラバラだと、素人感や場当たり感が出てしまい、知らず知らずのうちに信頼を落としてしまいます。ガイドラインを通じて細部まで統一することが、結果的にプロフェッショナルなブランドイメージを担保することにつながります。
社内外での効率化
ロゴガイドラインを整備しておくことで、社内外の業務効率を大きく向上させることができます。社内では、色やサイズ、使用可否に関する確認や判断がスムーズになり、制作・チェックにかかる時間を削減できます。社外の制作会社やパートナーに対しても、ガイドラインを共有するだけで要件を的確に伝えられるため、認識のズレや修正対応が減り、コミュニケーションコストの削減にもつながります。
多様な利用環境への対応
ロゴガイドラインを整備しておくことで、Webサイトや印刷物、アプリ、SNS など、多様な利用環境においても一貫したロゴ表現を維持できます。デジタル/オフラインごとの推奨サイズやレイアウト、多言語版ロゴの扱い方や各国の配色・コントラスト基準への対応方針を定めておくことで、グローバルな利用シーンでも品質を損なうことなく、統一されたブランドイメージを伝えやすくなります。
ロゴガイドラインの構成要素と作り方を解説!
実際にロゴガイドラインを作ってみたいけど、何をどのようにすればいいか分からない方に向けてセブンデックスのプレスキットを用いながら詳しく解説していきます。
構成要素1:ブランドロゴ

ブランドロゴは、その会社のシンボルとなるもので消費者との視覚的コミュニケーションにおいて最も重要な視覚的要素です。このデザインで正しく使用されないとブランドのイメージを正確に伝えることは難しくなります。そのためブランドロゴを表示する際には再現用データを作成し、その通りに使えば問題ないようにすることをおすすめします。
構成要素2:カラー

カラーを設定する主な理由は、ブランドの一貫性を保つためです。カラーが統一されていないと、ブランドとしての認識が曖昧になり、信頼性やイメージが損なわれる可能性があります。
たとえば、セブンデックスのように白と黒のみを使用している場合は、それほど細かい規定を設ける必要はありません。しかし、赤や青などの色を使用する場合、同じ赤でも濃淡や明度に違いが生じると、ブランドイメージが崩れる恐れがあります。そのため、オリジナルの色を色の三原色に基づくカラーコードで規定し、許容される濃淡の範囲を事前に設定しておくことが重要です。
さらに、ブランドの一貫性を考えるうえで「トンマナ」という概念が関わってきます。トンマナとは「表現全体の基調や調和」を意味し、ある要素が全体のスタイルやテーマとどのように調和しているかを示します。「トンマナを合わせる」という表現は、色調やスタイル、雰囲気を統一させることで、ブランドの印象に一貫性をもたせることを指します。
たとえば、広告やブランディングの分野では、企業や商品のイメージに合わせてカラーやデザインを統一させることが求められます。これにより、視覚的な印象が整い、ブランドの価値が高まるのです。カラーの規定とトンマナの整合性は、強いブランド構築に欠かせない要素と言えるでしょう。
トンマナに関して詳しく知りたい方はこちら!
構成要素3:最小サイズの規定

ロゴの最小サイズを規定する理由は、印刷物などでロゴが潰れてしまうことを防ぐためです。資料や印刷物でロゴが潰れて判別不能になると、企業やブランドの認識が困難になり、ブランドイメージが損なわれる可能性があります。そのため、ロゴが認識可能なギリギリの大きさを設定することが重要です。
最小サイズを設定する方法としては、名刺などの小さな媒体を想定し、ロゴを1ピクセルずつ縮小して印刷を行い、認識可能な最低サイズを目視で確認する工程を行います。このようにして、どのような場面でもブランドの認識性を損なわないための基準が作られます。
構成要素4:アイソレーション
アイソレーションとは、ロゴ周辺に確保される空白部分を指します。英語での「アイソレーション」は「独立」や「分離」を意味するため、一見すると「空白」との関連性がわかりにくいかもしれません。しかし、ここでいうアイソレーションは、ロゴやブランドの独立性を強調し、視認性を確保するために必要な空白を意味します。
この空白は、ロゴが他の要素に埋もれてしまうのを防ぎ、ブランドイメージを鮮明に伝えるための重要な役割を果たしています。

アイソレーションを設定する主な理由は、ロゴと社名、またはその他の要素が混同されないようにすることです。この空白によって、ロゴが独立した要素として認識されやすくなり、ブランドの一貫性と視認性が向上します。
アイソレーションの設定方法としては、ロゴの中で特徴的なパーツを基準にし、そのパーツの大きさを基準として空白を確保するのが一般的です。たとえば、セブンデックスのロゴを例に挙げると、ロゴの下部の長さを「X」と定義し、その「X」と同じ長さ分の空白を周囲に設ける、といった方法が用いられます。
この基準は、企業のロゴのデザインや特徴に応じて異なります。どの部分を基準にするかは、ロゴの全体的なバランスや視認性を考慮して決定されます。このような設定により、ロゴが他の要素と適切な距離を保ち、ブランドイメージが適切に伝わるようになります。
構成要素5:背景色
背景色を設定する主な理由は、ロゴが視認されない背景で使用されることを防ぐためです。ロゴがさまざまな媒体で使用される際、サイトやパンフレットなどの背景色によってはロゴが同化し、正しく認識されなくなる場合があります。また、背景色とロゴのコントラストが不十分だと、ロゴが見えにくくなり、ブランドの認識やイメージが損なわれる可能性もあります。
このような問題を防ぐため、背景色を設定し、ロゴが効果的に視認されるようにすることが重要です。具体的には、ロゴが使用できない背景色を事前に定め、ブランドガイドラインの中で明確に規定します。このプロセスは、ブランドの一貫性と視認性を確保するために欠かせない要素です。
構成要素6:使用禁止例
使用禁止例を設定する主な理由は、ロゴが形式を変えられて使用されたり、アイソレーションや背景色のルールが正しく守られていなかったりする場合に、顧客へのブランドイメージの低下を防ぐことです。
ロゴは、ガイドラインに沿ったデザインで使用されることで初めて、その本来の効果を発揮します。ガイドラインに反する使用が行われると、ブランドの一貫性が崩れ、信頼性や認識性に悪影響を与える可能性があります。
そのため、カラーやアイソレーション、背景色などのルールから逸脱した例を具体的に提示しておくことが重要です。これにより、使用者が誤用に気づきやすくなり、正しい利用が促進されます。結果として、ブランドの統一性と顧客への適切なイメージ伝達が保証されるのです。
セブンデックスでは、背景色や使用禁止例に関する具体的な規定は設けていません。このように、どの要素まで規定するかは企業ごとに異なります。それぞれのブランド特性や使用状況に応じて、どこまでルールを詳細に定めるべきかを検討することが重要です。企業のブランドイメージを棄損しないためにどこまで規定するべきかはしっかりと考える必要があります。
ロゴガイドラインの業界別事例
鉄道・公共インフラ
南海電鉄
南海電鉄のロゴガイドラインには、一般的なアイソレーション(余白)や最小サイズ、カラー指定(ブランドカラーである赤・オレンジ系の色指定)、背景別の使用例、変形や色変更などの使用禁止例が詳しく規定されています。ブランドシンボルとロゴタイプ、グループ会社ロゴなど複数バリエーションの使い分けも定められており、マスターデータを改変せずに使用することが求められています。ガイドライン自体はPDFで公開されており、社内外の関係者がダウンロードして参照できるようになっています。
大分市上下水道局
大分市上下水道局のロゴガイドラインは、シンボルマークの使用目的や禁止事項、申請が必要なケースを定めた内容になっています。商業利用や誤解を与える用途は不可で、原則として使用申請書の提出が必要です。ロゴの改変は禁止され、広報物やイベントで正しく使用することが求められます。ガイドラインと申請書類はPDFとして公開されています。
双葉町観光協会「FUTABA DARUMA」
双葉市観光協会「FUTABA DARUMA」のロゴガイドラインは、ロゴの使用目的、申請手続き、禁止事項を定めた内容になっています。復興PRや双葉町由来の製品・サービスに限り使用でき、ロゴの改変や単独での商品化は不可です。使用には原則として申請書の提出が必要で、色・比率・余白などの規定に従って正しく利用することが求められます。ガイドラインと申請書類は公式サイトで公開されています。
IT・SaaS・ソフトウェア・通信
SmartHR
SmartHR のロゴガイドラインは、ロゴの適切な使い方、サイズ・余白・カラー・禁止事項、使用対象および利用範囲を定めた内容になっています。ロゴは「横組ロゴを基本」に、背景や配色、最小サイズや余白のルールを守る必要があり、改変・影付け・傾斜などは禁止です。利用できる人・用途も限定されており、データ(PNG・SVG・AI)は公式サイトからダウンロード可能です。
PIXTA
PIXTA のロゴガイドラインは、ロゴの使用目的・使用条件、禁止事項を明確に定めた内容になっています。使用は、サービス紹介・提携・クリエイター表示などの正当な目的に限られ、改変・ロゴの一部使用・承認なしの推薦表現などは禁止です。さらに、ロゴの最小サイズ・保護余白・色指定も規定されており、使用継続にはルール順守が求められています。
Microsoft
Microsoft の商標ガイドラインは、ロゴや名称などすべてのブランド資産の正しい利用方法を定めた内容になっています。ロゴの改変や誤解を招く使用は禁止され、利用には明確な条件やライセンスが必要です。最小サイズや余白などの仕様も細かく規定されています。ガイドラインは公式サイトで公開されています。
学校法人
東京大学
東京大学のロゴガイドラインは、新VI「UTokyo」を中心に、学内外での使用条件や申請手続きを定めています。ロゴは構成員や指定組織のみ利用でき、営利目的には原則申請が必要です。色・比率・配置などのデザインルールも詳細に規定されています。ガイドラインは公式サイトで公開されています。
慶応義塾大学
慶應義塾大学のロゴガイドラインは、ペンマーク・三色旗・ロゴタイプの一体的な使用基準をまとめた内容です。無断利用は禁止で、データ取得には正規手続きが必要となります。シンボルの改変や誤用を防ぐためのデザインルールも整備されています。資料は公式サイトから確認できます。
行政・自治体・国際機関・財団
国土交通省
国土交通省のシンボルマークは、原則として第三者利用を認めず、委託・後援等に該当する場合のみ使用が許可されます。商業利用や誤解を招く用途は不可です。申請が必要なケースや禁止事項が明確に整理されています。詳細は省の公式ページで公開されています。
流山市
流山市のブランドマークは、市民や事業者が幅広く利用できる一方、使用には申請書の提出が必要です。商用利用も可能ですが、改変は禁止され、所定のガイドラインに従った正しい使用が求められます。ブランドのイメージを損なう用途は禁止されています。ガイドラインは市の公式サイトに掲載されています。
日本財団
日本財団のロゴガイドラインは、助成表示マークを含むロゴの正しい使用方法を定め、拡大縮小以外の一切の加工を禁止しています。助成事業における表示義務や使用条件も詳細に規定されています。適切なサイズ・色での使用が求められます。ガイドラインとデータはPDFで公開されています。
NASA
NASA のブランドガイドラインは、インシグニア・シール・“Worm” ロゴの厳格な使用基準を定めています。商業利用や広告目的での使用は法律上禁止され、誤認や改変も不可です。利用には特定の例外以外ほぼ許可されません。ガイドラインはNASA公式ブランドセンターで公開されています。
メーカー系
The North Face
The North Face のブランドガイドラインは、ロゴのクリアスペース・配色・サイズなどを定め、改変・視認性を損なう使用を禁止しています。コラボレーション時のロゴの優先順位や配置ルールも詳細です。ブランドの統一性を守るため厳格な管理が求められます。資料は公式サイトで提供されています。
Columbia
Columbia のブランドガイドラインは、ロゴおよびグラフィックの所有権と使用条件を定めた内容になっています。ロゴの無断利用や改変は禁止され、適切な色・比率での使用が求められます。具体的な利用には個別の許可が必要となる場合があります。情報は公式サイトで確認できます。
ロゴガイドラインの運用方法
ガイドラインの整備と認知
ロゴガイドラインは作成して終わりではなく、まず「整備」と「認知」をセットで進めることが重要です。ロゴの基本ルールだけでなく、使用例・NG例、媒体別の推奨パターンなどを整理し、誰が見ても迷わず使える状態にしておきます。そのうえで、社内ポータルへの掲載や周知メール、勉強会・デザイン相談窓口などを通じて、関係部署に存在と目的をしっかり浸透させます。とくに営業・広報・採用など外部向け資料を扱う部門には重点的に案内し、「ロゴを使うときはまずガイドラインを見る」という行動を社内の共通ルールとして定着させることが大切です。
使用可能範囲と権利の明確化
ロゴガイドラインでは、誰が・どのような目的で・どの媒体にロゴを使用できるのか、といった「使用可能範囲」と著作権・商標権などの「権利関係」を明確にしておくことが重要です。社内利用と社外パートナー利用の違いや、二次加工の可否、申請・承認フローなどを具体的に記載しておくことで、無断利用や不適切な改変を防ぎつつ、トラブルリスクを低減できます。また、利用ルールがはっきりしていることで、担当者は安心してロゴを活用でき、ブランド価値を守りながらプロモーションを推進しやすくなります。
使用ルールの遵守
使用ルールを定めるだけでなく、それを確実に守ってもらう仕組みを整えることが重要です。ロゴを扱う部署にはガイドライン説明会やマニュアル共有を行い、制作物の公開前チェックフローもあわせて設けます。ルールから外れた事例があれば、その場限りで修正して終わらせず、なぜNGなのかを共有し、ガイドライン自体の改善にも反映させることで、運用レベルでの遵守を継続的に高めていくことができます。
社内外への浸透
ロゴガイドラインを実効性のあるものにするには、社内外への浸透が欠かせません。社内向けには、イントラ上での公開や定期的な周知、説明会の実施を通じて、「ロゴ利用時は必ず確認する」という共通認識を育てます。社外向けには、制作会社やパートナー企業向けに配布用データとあわせてガイドラインを共有し、契約書や発注書にも参照先を明記することで、どの関係者も同じルールに基づいてロゴを扱える環境を整えることが重要です。
ロゴに関してはセブンデックスへ
本記事では、ロゴのガイドラインに関する重要性や具体例について解説しました。セブンデックスでは、業界特有の課題に対応しながら、企業のロゴデザインから、そのロゴを活用したブランディングやPR活動まで幅広くサポートを行っています。
自社の価値をさらに高めたい、あるいはロゴを効果的に活用して効率的なブランディングを実現したいとお考えの方は、ぜひセブンデックスにご相談ください!